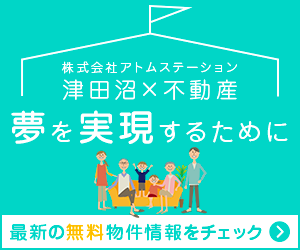私はキッチン研究家の田辺です。
今回は、2023年3月に放送されたスペシャルドラマ「キッチン革命」について、私なりの感想を書きたいと思います。
ドラマ「キッチン革命」のあらすじ
このドラマは、戦後の日本で公団住宅の設計に携わった建築士・浜崎マホと、栄養学の第一人者・香美綾子の物語です。
まだ女性の社会進出に消極的なイメージを持たれていた時代に、二人はそれぞれの分野で日本の台所に革命を起こそうと奮闘します。
マホは欧米式のダイニングキッチンを提案し、ステンレス製の流し台を開発します。
綾子は料理カードを作り、栄養学を多くの女性に広めていきます。
ドラマ「キッチン革命」から見える昔のキッチン
私はこのドラマを見て、感動しました。
なぜなら、私自身がキッチンに関心があるからです。
私は若い頃、フランスへ料理の勉強に出ていたことがあり、そのときに日本とは全く違うことに驚きました。
仲良くなった同僚の家にお邪魔した時に、フランスのキッチンは広くて明るくて、そこにはコミュニケーションがとりやすい空間がありました。
そのキッチンもとい食卓では、家族や友人と一緒に料理を楽しみながら食事をすることができました。
それに比べて、当時の日本のキッチンはまだキッチンは別の部屋の家が主流で、隔離されていました。
男は台所に踏み入らない時代でもあったため、私の母も一人でせっせと料理をしていたのを思い出します。
そんなキッチンでは、料理も食事も楽しくありませんよね。
ドラマ「キッチン革命」で分る現代の文化とは
ドラマ「キッチン革命」では、公団住宅という限られたスペースの有効活用で欧米スタイルのダイニングキッチンが提案され、また主婦の重労働を改善するためにステンレス製の流し台作りを軌道に乗せています。
今ではすべてが当たり前に使われているものばかりです。
そして、料理カードは分量や手順が明確に書かれているので、誰でも美味しく栄養のある料理が作れます。
これも、現代だとネットで手軽に分量がわかる料理の作り方として見ることができますよね。
こういった、ゼロから一を作り上げた先人たちがいるお陰で、我々は皆で食卓を囲み、時には代わる代わるキッチンに立ちながらコミュニケーションを取りながら生活することができています。
私はこのドラマを見て、マホや綾子に感謝しました。
まとめ
ドラマ「キッチン革命」では、戦後の食についてや住まいについての歴史が紹介されていました。
それに沿って、栄養学がどう進歩したのか、住宅の台所事情がどう変化したのかを教えてくれました。
彼らがいなければ、今の私のキッチンも生活もありませんでした。
私はこれからもキッチン研究家として、キッチン革命に貢献したいと思います。
そして、みなさんにもキッチン革命に参加してほしいと思います。
キッチンを変えれば、生活も変わります。
楽しく美味しい食事をしましょう。
それでは次回、お会いしましょ。